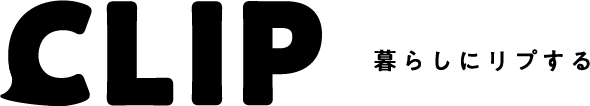「YouTube」や「Twitch」など、動画配信サイトの登場で一般的になった“ゲーム実況”。有名タイトルやマイナータイトルなど、数多くの配信者が日夜ゲームを紹介しています。この記事では、現役でゲーム配信を行っている筆者がゲーム実況の始め方を徹底解説! ゲームや配信サイトの選び方、配信における注意点をまとめて紹介します。
ゲーム実況を始めてみたいと思っている方は、是非参考にしてください。
ライター:荒井啓仁
あなたにピッタリのインターネットは?
まずは「どんな実況をしたいか」はっきりとさせる

ゲーム実況を始めたい場合、機材や配信プラットフォームを選ぶよりも先に考えたいのが「どんな実況をしたいか」。
“ゲーム実況”と一口に言っても「やりたいゲームをひたすらライブ配信する」「好きなゲームの攻略情報を動画で投稿する」など、さまざまな活動方法があります。ライブ配信にせよ動画投稿にせよ、まずは自分がどういう形で活動をしていきたいのか、しっかり向き合うことが大切です。
とはいえ、始める前にあれこれ考えこんで悩んでしまっては本末転倒。方向性に悩んだら、自分が好きな配信者やテレビ番組をしっかり見返すのがおすすめです。自分自身が感じる「好きだな」「見ていて楽しい」という気持ちをベースにすれば自然と方向性が見つかるでしょう。
ゲームや配信サイトの選び方

“ゲーム実況”である以上、配信・投稿するタイトルや配信サイトを選ぶ必要もあります。ゲーム実況初心者が最初につまづく可能性のあるゲームや配信サイトの選び方を紹介します。
ゲームの選び方
「好きなゲーム」「話題のゲーム」など、実況するゲームの選び方は多種多様です。話題のタイトルであれば視聴回数が伸びやすいかもしれませんが、それだけ競合も多いということ。飽きずに続けられるように、自分の好きなタイトル、好きなジャンルにするのがおすすめです。チャンネルとしてしっかり方向性を決める場合は、「ホラーゲーム専門」「アクションゲーム専門」など、実況するゲームのジャンルを絞るのもよいでしょう。
関連記事:代表的ゲームジャンル8種 サブジャンル・作品例も徹底解説
関連記事:オンラインゲーム歴19年の筆者おすすめ、「今からでも始めやすい」タイトル10選【ジャンル別】
配信サイト選び
ゲーム実況ができるプラットフォームは数多くありますが、ユーザーが集中しているのは、YouTubeとTwitchの2つ。それぞれの特徴を紹介します。
YouTube
「YouTube」は言わずと知れた動画投稿サイト。録画済みの動画投稿の他にライブ配信機能としての「YouTubeライブ」もあります。YouTubeの特徴はなんといっても桁違いのユーザー数。他のプラットフォームを圧倒する数のユーザーに向けて配信できるため、配信や動画投稿の幅が大きく広がります。もともとが動画投稿サイトなので、配信+動画投稿など、活動の幅を広げやすいのもおすすめ。他の配信プラットフォームで動画配信をしつつ、YouTubeにはアーカイブや切り抜き動画をアップするというスタイルの配信者も多数存在します。
Twitch
ゲーム配信に特化した動画プラットフォーム「Twitch」。動画投稿は行えませんが、自身の配信を記録として取っておくアーカイブ機能があります。YouTubeと比べて全体のユーザー数は少ないですが、ゲームに特化しているため、ゲーマー向きの配信を行いたい方にはおすすめのプラットフォームです。視聴者との交流機能が多くあり、ポイント数を貯めることで配信者側にアクションを行うこともできます。人気の集まる配信の傾向としては「ゲームのうまさ」が重要なポイント。トーク力ももちろん大事ですが、プレイに華がある配信を求めているユーザーが多い印象です。ゲームの腕前に自身がある配信希望者はTwitchでの配信を検討してもいいかもしれません。
同時配信ってどうなの?
配信ソフトの設定によっては複数の配信サイトに同時配信することも可能です。ただ、規約上で「配信画面に別サイトでのコメントを表示するのは禁止」など、制約がかかっている場合がほとんど。また、ユーザーの雰囲気もプラットフォームごとに違うので、一方のコメントばかり反応すると、もう一方のユーザーが不満を覚えることも考えられます。通信回線やパソコンへの負担も大きいので、同時に配信したい場合はメリット・デメリット・規約を総合的に検討したほうがよいでしょう。
ゲーム実況を始める際の注意点

“ゲーム実況”とは、いわば「自分が購入したゲーム内容を不特定多数に公開する」行為に他なりません。誰もが気軽に行っているからこそ、気をつけたいポイントは多くあります。
ゲーム開発者へのリスペクトを忘れずに
“ゲーム実況”をする上で最も大切にしてほしいのはゲーム開発者へのリスペクト。ゲーム実況を始める際は、あくまで“遊ばせていただいている”立場であることを十分に理解する必要があります。ゲーム配信に多くの視聴者が集まっても、そのまま収益がゲーム開発者に還元されることはありません。無料で不特定多数にゲーム内容を公開する以上、ゲーム公式サイトやストアページへのリンクを掲載するなど販売元や制作者の利益に少しでもつながるように工夫しましょう。ゲーム規約にしっかり目を通すことも大切です。
著作権について
数え切れないほどの動画が存在し、なんの問題もないように見える“ゲーム実況”。ゲーム内容やゲーム画面・音楽などは開発者や販売元などが著作権を保有しています。著作権者の許可なくインターネット上の配信を行うと、著作権法の「公衆送信権」などの侵害にあたることがあります。ただゲーム実況が一般的になってきた現代では、ガイドライン上でゲーム実況の許可を与えているケースも多くあります。ゲームを配信したい場合は、タイトルやストアページのガイドラインや配信規約をしっかりと確認しましょう。万が一公開されていない場合は、販売元の会社に確認を取る必要もあります。
配信前、必ず規約の確認を
既存の実況動画が多数あるタイトルでも、規約の確認は必ず自分自身でしっかりと行いましょう。タイトルによっては「配信NG」や、「一部ストーリーの公開禁止」など、細かいルールが設定されていることもあるので、熟読は必須です。なかには収益化を禁止しているタイトルもあるため、ゲーム実況を続けるのであれば、規約の確認を癖付けておくとよいでしょう。
配信時に避けたほうがいい話題・映さないほうがいいもの
自由なトークを売りにする配信者も多く活動し人気を集めていますが、一般的に避けたほうがいい話題については触れないほうが得策です。ゲーム内容への批判を超えた誹謗中傷や差別用語ももってのほか、そして不快に思う人が存在しうる話題も当然避けましょう。
また、配信画面には個人情報が映らないように注意。ブラウザ画面を映した際、通販サイト上で本名や住所が映ってしまうトラブルはよくあるため、気をつけましょう。
配信者が未成年の場合は?
不特定多数が見るゲーム実況では、悪意を持ったユーザーがコメントしてくる場合も考えられます。コメントにおだてられて、顔や個人情報を映してしまえば取り返しのつかないトラブルに発展するかもしれません。もし未成年でゲーム実況を行いたい場合は、配信や投稿活動に対してしっかりと相談できる保護者の協力が不可欠です。
視聴する際にも気をつけたいポイント
ゲーム実況を視聴する際は、配信のマナーに気をつけたいところ。各チャンネルによってルールを決めている場合は、必ず従いましょう。一般的には、配信者の許可なく宣伝行為(自分自身や第三者、外部コンテンツの紹介など)をコメント欄で行うのは、ゲーム実況に限らず配信全般でNGです。配信者によっては内容を問わずブロックされることもあるので、気をつけましょう。
「過度な自分語り」や「セクハラ・パワハラ」「行き過ぎた指示コメント」は、ほとんどの配信者が嫌うので要注意。自身が視聴者として他チャンネルのチャットに参加する際は、コメント欄の空気を見極め、配信が盛り上がるようなコメントを心がけましょう。
ゲーム実況に必要なもの

ゲーム機によっては、特別な機材がなくてもゲームのプレイ画面と音声をミックスし、動画サイトに投稿する機能もあります。もちろん内蔵の機能でゲーム実況を投稿することもできますが、機材を活用した実況より品質は劣ります。この項では、一般的なゲーム実況に必要なものを紹介します。
PC
ゲーム実況を行う上で、できれば用意したいのがPC。スマートフォンやゲーム機だけでも実況自体は行えますが、配信のしやすさや投稿・編集を考えれば、PCはあるに越したことはありません。後述するマイクやカメラなど、使える機材の幅も広がりますし、配信ソフトを利用することで、配信や動画投稿がより簡単に行えます。ただし、「PC上でゲームを動かしながら配信をする」ためにはある程度スペックの高いPCが必要になる点は注意しましょう。スマートフォンやゲーム機で配信や動画投稿に慣れておいて、PCに移行するというのもアリです。
スマートフォン
通話に動画撮影も行えるスマートフォン。スマートフォンでゲーム画面を直接撮影しながら配信や投稿を行うというのも、技術的には可能です。ただ視聴者側として見た場合、「性能の悪いマイク」と「カメラで直撮りしたゲーム画面」の配信や動画を見たいという視聴者は少ないかもしれません。スマートフォンのゲームを実況したい場合もマイク音声が配信などに乗せられないこともあるため、できればPCを用意したほうがよいでしょう。
ゲーム機
PCでのゲームプレイが一般的になってきましたが、ゲーム機を用意するメリットも多くあります。ゲーム機専用タイトルを実況する場合には不可欠なのはもちろん、パソコンのスペックが足りない場合にも一役買います。PCでゲームを映しつつ配信を行うのは、それなりにスペックの高いPCが必要になります。PCのスペックが低い場合は「ゲームの処理をゲーム機で行い、PCは配信に集中する」ことが可能になるのです。
マイク
読み上げソフトを利用したゲーム配信や実況も多いですが、自身の声を乗せたいという人も多いはず。配信や動画で意外と大事なのがマイクの品質です。どんなに内容が面白くても、「雑音が多い」「声が途切れる」といった音のトラブルでは視聴がストレスになってしまいます。もちろん内容が一番大切ですが、音声の品質が悪いと、配信や動画の途中離脱につながるのです。コンデンサーマイクやダイナミックマイクなど、ご自身の収録環境に合ったマイクを選びましょう。
カメラ(実写でもVtuberでも)
実写はもちろん、顔を隠す配信でもカメラはマストアイテム。Vtuberでの活動を目指す場合もモーションキャプチャーなどが必要になります。ゲーム実況では、ゲーム画面の比率が多くなるのでそこまで高画質なモデルではなくても、問題ありません。実写で配信する場合は高画質のものよりも色味の補正がしっかりとできるものがおすすめです。
配信ソフト
PCで配信する場合は、ぜひ配信ソフトを導入しましょう。配信ソフトとして有名な「OBS Studio」は、プラグインが多くあり、使っているユーザーが多いため何かのトラブルが起きても調べて解決しやすいのでおすすめです。Vtuberとして活動するのであれば、モーションキャプチャー用のアプリなど、専用ソフトも必要です。
サブモニタ(あれば)
メインモニターでゲームをプレイしながら、配信ソフト等の設定を調整することができるため、導入がおすすめ。PCでのゲーム実況を考えているのであれば、ぜひおすすめしたいのがサブモニタの導入。PC上でもゲーム機でも、ゲーム画面をメインに映しつつ、サブモニタで配信画面などを操作が可能です。もちろん、サブモニタがなくてもゲーム実況は行えますが、一度使ってしまうともうサブモニタなしの実況は考えられないほどの快適さ。画質やフレームレートは考慮せずに、格安モニタなどでも十分利用できるので、検討してみてください。
有線の通信回線
PC・ゲーム機、どんなデバイスだったとしても、ゲーム実況を行うには有線の通信回線を用意しましょう。とくにライブ配信の場合は、遅延や画面・音声の乱れ、接続が切れてしまう可能性もあるため、安定した通信回線は必須です。動画投稿だけの場合でも素材のダウンロードやアップロードなど、快適な活動を行うためには無線接続では厳しい部分も多いでしょう。特別な理由がない限り、ゲーム実況を行う場合は有線でのインターネット接続をおすすめします。
まとめ
インターネットの高速化とパソコンの高スペック化で、誰でも気軽に行えるようになった“ゲーム実況”。気軽に行えるからこそ、著作権上の問題や配信でのマナーには一層の注意が必要です。好きなゲームを楽しく遊ぶ姿を視聴者に見せることができれば、1人また1人と、少しずつでも視聴者が増えていくはず。高価な機材がなくても始める手段はあるので、まずはお試しでも始めてみるのがおすすめですよ。
配信でも動画投稿でもゲーム実況を快適に行うには、安定かつ高速な通信回線が必要不可欠です。もしお使いの通信回線に不安がある場合は、回線契約を見直してみてはいかがでしょうか?
【関西でネット回線をお探しなら】
eo光は18年連続お客さま満足度 No.1!※
※RBB TODAY ブロードバンドアワード2024 キャリア部門 エリア別総合(近畿)第1位(2025年1月発表)
2007年~2024年18年連続受賞。
※上記掲載の情報は、取材当時のものです。掲載日以降に内容が変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。