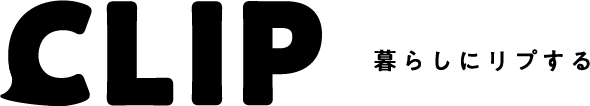写真や音楽、動画など、インターネットの高速化にともない、いちファイルのデータ容量がどんどん増えていく現代。スマホやPCからあふれてしまうデータを保存するために、さまざまな記録媒体が販売されています。今回は、HDDやSSDから光学ディスク(CDなど)まで、身の回りにある記録媒体をまとめて紹介。最大容量の目安や耐用年数、それぞれの特徴も詳しく解説します。
ライター:CLIP編集部
あなたにピッタリのインターネットは?
1.HDD

最大容量:〜24TB
(2025年10月時点の通販サイトで購入可能なHDDでの最大容量:CLIP調べ)
耐用年数:一般的に3〜5年程度が目安
大容量の記録媒体といえばHDD(ハードディスク)を思い浮かべる方も多いかもしれません。HDDは磁気ディスクによる記録媒体で、パソコンに内蔵されていたり外付けの商品が販売されていたりと、PC周りで利用されることが多い媒体です。後述するSSDよりも安価で容量が大きい記録媒体として広く利用されています。市販品では24TBの超大容量モデルも販売されており、大量のデータを取り扱う場合にはおすすめです。
向いている用途・目的
HDDはSSDに比べてコストが低いことから、予算を抑えて大量のデータを保存したいような場合におすすめな記録媒体です。パソコンのバックアップ用や事業所などで保存する書類データなど、データ容量が大きく長期間安全に保存しておきたいようなデータを取り扱う際には最適といえるでしょう。
注意点・メンテナンス方法
HDDを使う上での注意点は、衝撃や高温、多湿、ホコリなどの利用環境。PC内蔵の記録媒体がHDDの場合は移動時に電源を切ったり衝撃が伝わらないようなケースに入れるなど工夫が必要です。安定した環境なら利用に問題はありませんが、長時間使うと故障率が上がってしまう点も注意しましょう。熱がこもらないよう、PCや外付けHDDはホコリの除去などをこまめに行うと負荷がかかりづらくなります。
2.SSD

最大容量:〜8TB
(2025年10月時点の通販サイトで購入可能なSSDでの最大容量:CLIP調べ)
耐用年数:5年〜10年程度(目安)
物理的な磁気ディスクを利用するHDDと違い、フラッシュメモリ(半導体メモリ)にデータを記録する記憶装置がSSD(ソリッドステートドライブ)。HDDよりも高速で読み書きでき、容量の大きいデータを頻繁に扱う場合に便利です。HDDに代わり標準でSSDを搭載したパソコンも増えてきています。HDDのような「ディスクの回転」や「ヘッドの移動」といった可動部品がないため、HDDと比べて衝撃に強く、排熱や振動・騒音がない点もSSDの特徴です。
向いている用途・目的
動画やゲームなど、容量の大きいデータを頻繁に読み書きする必要がある場合は、SSDの導入がおすすめです。また、パソコンの起動ディスクをSSDすることで、パソコンの起動もスピーディーに。HDDのようなディスクの回転やヘッドの移動といった可動部品がないため、SSDは動作音や振動がほとんどなく、パソコンの音が気になる場合にも適しています。
注意点・メンテナンス方法
HDDと比べると衝撃に強いSSDですが、とはいえ電子部品のため過信は禁物です。高温に弱く、一度不具合が出てしまうとデータの復旧が難しい点は覚えておきましょう。また、HDDと同じく、長時間の利用になると劣化していく点も注意が必要です。
関連記事:SSDとは?メリット・デメリットとスペックの見方
関連記事:SSDとHDDの違いとは?それぞれのおすすめの利用方法
関連記事:SSDの寿命は何年?長く使用するためのポイント
3.USBメモリー

最大容量:〜2TB
(2025年10月時点の通販サイトで購入可能なUSBメモリーでの最大容量:CLIP調べ)
耐用年数:10年以上使えるものもあるが、3年程度のものが一般的
ポケットに入る小さいサイズの記録媒体であるUSBメモリー。持ち運びしやすく、データの受け渡しなどに向いています。データの長期保存よりは短期保存に向いた媒体といえるでしょう。低容量のモデルが一般的ですが、2TBの大容量のモデルも販売されています。
向いている用途・目的
USBメモリー最大の利点は持ち運びのしやすさ。メールやクラウドサービスで共有しづらい容量の大きいデータを共有する際に役立ちます。
注意点・メンテナンス方法
USBメモリーはフラッシュメモリを利用した記録媒体。読み書きできる回数には上限がある点は注意が必要です。一般的に3年程度は問題なく利用できますが、製品によって寿命が異なるのでしっかりと確認しましょう。また、水分にも弱いので「コーヒーをこぼしてしまった」などの日常的なトラブルにも注意が必要です。そして小さく運びやすいだけに、紛失には十分気を付けたいところです。
データの持ち出しやコンピュータウイルス等の感染の対策として業務用パソコンなどではUSBメモリー自体の使用を禁じられている場合があるのでその点も注意しましょう。
4.SDカード

最大容量:〜512GB
(2025年10月時点の通販サイトで購入可能なSDカードでの最大容量:CLIP調べ)
耐用年数:3〜5年程度
SDカードは小さいカード状の記録媒体。カメラやスマートフォン、ゲーム機などに利用されています。SDカードは、切手ほどの大きさの「SDカード」と、指先に乗るほど小さい「microSDカード」の2種類の形状があります。
向いている用途・目的
デジタルカメラユーザーにはおなじみのSDカード。容量の大きいSDカードを使えば、長時間の録画や大量の写真を保存しておけます。専用リーダーがあればパソコンでのデータ整理や共有も可能です。
注意点・メンテナンス方法
とにかく小さいSDカード。小型なだけではなく薄いため破損には最大限の注意を払いましょう。専用ケースや持ち運び用の小箱を利用するなど、複数枚持ち運ぶ際は工夫が必要です。そしてもちろん紛失にも十分な注意しましょう。使い終わったら必ずケースや定位置に戻す習慣をつけるといいでしょう。そして書き込み速度や書き込み回数など商品によって異なる点も注意しましょう。
5.光学ディスク

CD
最大容量:約700MB(標準的なCD-R/CD-ROMの場合)
DVD
最大容量:4.7GB~17GB(両面2層)
BD
最大容量:25GB(1層)、50GB(2層)、100GBまたは128GB(BDXL規格)
(2025年10月時点の通販サイトで購入可能な製品での最大容量:CLIP調べ)
耐用年数:おおよそ10年〜30年程度
光学ディスクとは、音楽や映像など、さまざまな商品としても活用されているCD、DVDのこと。音楽や映像作品として市販されている商品は、主に「読み込み専用」ディスクですが、個人がデータを書き込める「書き込みが可能」なタイプ(CD-R、DVD-R、BD-Rなど)も広く販売され、利用されています。家庭用レコーダーで録画した番組の保存や、パソコンのデータバックアップなど、個人用途としても活用されています。
向いている用途・目的
光学ディスクはUSBメモリーやSDカードと比べても安価なのが特徴です。単価が低いので、配布用の資料などにも活用されています。家庭での利用としては、レコーダーで録画した番組を保存したい場合にも便利です。
注意点・メンテナンス方法
耐用年数が比較的長い光学ディスクですが、高温多湿に弱いため保存環境には注意が必要です。また、読み取り面が傷ついてしまうだけで利用できなくなってしまうので、取り扱いには気をつけましょう。長期間保管する場合は、ケースを立てることでゆがみや反りを防げます。
またパソコン自体に読み込み・書き込みドライブが搭載されていないものも近年は多いため、記録・再生環境がない可能性がある点にもあらかじめ注意しましょう。
破損や紛失のリスクを避けるにはクラウド利用もおすすめ

物理的な記録媒体には破損や寿命がつきもの。不意のトラブルで保存していたデータが消えてしまう可能性はゼロではありません。他人と共有する際に実際に受け渡す必要があるなど、業務などでは利用が難しい場合も考えられます。「できる限りデータを失いたくない」「複数人で共有したい」という場合は、クラウドストレージでの保存もおすすめです。
まとめ
データを大量に保存できたり持ち運びできたりと、記録媒体にはさまざまな特徴とメリットがあります。用途や目的に合わせて最適な記録媒体を選びましょう。パソコンやスマートフォンのバックアップや絶対に失いたくないデータの保存には、物理的な記録媒体とあわせてクラウドストレージも利用するのもおすすめです。クラウドストレージで容量の大きいデータを扱う場合は、高速かつ安定した通信環境が必要です。お使いの回線に不満や不安がある場合は、回線契約の見直しを検討するのもおすすめです。
【関西でネット回線をお探しなら】
eo光は18年連続お客さま満足度 No.1!※
※RBB TODAY ブロードバンドアワード2024 キャリア部門 エリア別総合(近畿)第1位(2025年1月発表)
2007年~2024年18年連続受賞。
※上記掲載の情報は、取材当時のものです。掲載日以降に内容が変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。