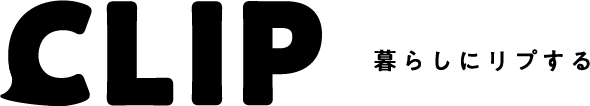SSDは、パソコンの記憶媒体や外部ストレージとして幅広く活用されています。長くSSDを使っていると「このまま使い続けていいのだろうか?」と不安を感じることもあるでしょう。そこで今回は、SSDの寿命の目安や長く使用するためのポイントについて紹介します。
ライター: CLIP編集部
あなたにピッタリのインターネットは?
SSDの寿命の目安は?

SSDの寿命の目安や寿命の指標となる数値について解説します。
SSDの寿命の目安
SSDは「Solid State Drive(ソリッドステートドライブ)」の略称で、データを保存するためのストレージとしてパソコンの内部に搭載されているほか、外部ストレージとして販売されています。
SSDの寿命は一般な家庭用・ビジネス用途では5~10年程度とされていますが、商品によって設定されている期間は異なるほか、メーカーが推奨する期間を超えても問題なく動作するケースもあります。
逆に、使い方が悪いと期間を迎える前に故障するケースもあるため「5~10年」という期間はあくまで目安として考えることが大切です。
SSDの寿命の指標は?
SSDの寿命はどのような基準で計算されているのでしょうか? ここでは、SSDの寿命の指標とされる「TBW」「DWPD」について解説します。
【TBW】
TBWは「Tera Byte Written(テラバイトライトゥン)」の略称で、SSDに合計でどの程度のデータを記録できるかを示した数値です。
例えば、SSDのTBWが3,000の場合、合計で3,000TBのデータを記録できることになり、SSDに記録した総データ量が3,000を超えると寿命が近いと判断できます。
TBWの数値は、SSDの取扱説明書や公式Webサイトに記載されている商品情報で確認できるため、寿命を確認したい方は一度チェックしてみましょう。
【DWPD】
DWPDは「Drive Writes Per Day(ドライブライトゥンパーデイ)」の略称で、SSDの耐久性を示す指標です。
メーカーが設定した保証期間中に、1日あたりどの程度の書き換えが可能なのかを示しています。
容量3TBで保証期間6年/DWPD20の場合、毎日60TB(3TB×20回)のデータを書き換えても6年間(メーカーが設定した保証期間)は正常に動作するということになります。
なお、TBWとDWPDの数値は商品によって異なります。購入時にこれらの指標を確認すると、SSDのおおよその寿命を把握できます。
ただし、使用する環境や使い方などによってSSDの劣化スピードは変わるため、絶対的な指標にはならないことを覚えておきましょう。
SSDの寿命を縮める使い方

以下のような使い方はSSDの寿命を縮めることにつながるため注意しましょう。
空き容量が少ない状態で使い続ける
SSDの空き容量が少ないと、保存可能なスペースが限られるため、データの削除や書き込みが頻繁に行われます。このような動作が繰り返されるとフラッシュメモリに余分な負荷がかかり、SSD自体の劣化が進んでしまいます。
書き込み回数が多い
TBWの項で紹介したように、SSDには書き込み可能な総データ量の上限があります。頻繁にデータの書き込みを行うと短い期間でTBWの上限に達し、フラッシュメモリの劣化が進んでしまいます。その結果、寿命の目安よりも早くSSDに不具合が発生する可能性があるため注意しましょう。
長時間の連続使用
長時間の連続使用もフラッシュメモリに負荷を与え、SSDの寿命を縮める原因になりえます。数時間使用後は休憩を挟むなど、連続使用が繰り返されないように注意しましょう。
高温・低温・多湿などの外的環境
高温多湿や極端な低温など、外的環境が電子部品の劣化を早め、動作不良やデータの破損を引き起こすことがあります。SSDは、「冷却部にホコリや汚れが溜まる」「負荷の高いアプリを長時間連続使用する」などによっても熱が溜まりやすいので、メンテナンスや使い方に注意しましょう。
また、SSDはHDDに比べて衝撃や振動に強いとされていますが、ダメージがない訳ではありません。ノートパソコンや外付けSSDを持ち運ぶ際には、できるだけ衝撃や振動を与えないように注意しましょう。
SSDの寿命が近づいたときの症状

SSDが寿命に近づくとどのような不具合が発生するのでしょうか? SSDを搭載したパソコンにあらわれる主な症状について解説します。
パソコンがフリーズする
作業中に突然パソコンがフリーズする、動作が止まってしまうといった現象は、SSDに不具合が発生している場合の代表的な症状です。
これは、SSD内部の記憶領域が劣化し、データの処理が正常に行えなくなることで発生します。こうした症状が見られた場合は、早めにバックアップを取ってデータを保護しましょう。
パソコンの買い替えが難しい場合は、データをバックアップした上で、業者やメーカーにSSDの交換を依頼するという方法もあります。
処理速度が低下する
以前よりもファイルの読み込みや保存に時間がかかる、アプリの起動が遅いなど、パソコンの動作がもたつくようになった場合も注意が必要です。
SSDは寿命が近づくと、書き込み速度や読み込み速度が著しく低下することがあります。処理速度の低下は、作業のストレスだけでなく、SSDの深刻な劣化の前兆である可能性もあるため放置しないことが重要です。
SSDが認識されない
パソコンが起動時にSSDを認識せず、「Boot Device Not Found(ブートデバイスが見つかりません)」といったエラーメッセージが表示される場合、SSDが正しく動作していない可能性があります。
SSDが認識されなくなると、保存していたデータにもアクセスできなくなってしまうことがあるため、不具合の前兆が見られた時点で早めにデータをバックアップしましょう。
保存したファイルに不具合が発生する
ファイルの不具合は、パソコンだけでなく外付けSSDにも発生する症状です。
SSDの劣化が進行すると、保存していたファイルにアクセスできなくなったり、ファイルが破損して開けなくなったりすることがあります。特定のファイルだけが読み込めない、または一部の内容が消えてしまっているといった不具合は、SSDの寿命が近づいている兆候です。
このような症状が確認された場合は、データのバックアップを行ったうえで、買い替えや業者・メーカーへの交換依頼を検討しましょう。
SSDの寿命を延ばすためのポイント

SSDの寿命を延ばすためのポイントについて紹介します。
一定の空き容量を維持する
SSDの空き容量が不足した状態で使い続けると、フラッシュメモリへの負荷が増加し、寿命が短くなります。不要なファイルやデータ、使用していないソフトやアプリを定期的に削除し、容量に余裕を持たせて使用しましょう。
パソコンを使わないときはシャットダウンする
パソコンの使用後は、スリープモードではなくシャットダウンをすることで、SSDへの負荷を軽減できます。スリープモードではバックグラウンドでまれにSSDへの書き込みが発生することがあるため、長時間試用しない場合はシャットダウンするようにしましょう。
使用環境や保存方法に注意する
温度や湿度、ホコリや汚れなどもSSDに負荷を与えてしまいます。
「湿気が溜まっている場所や直射日光が直接当たる場所に保存しない」「パソコンの冷却性能が低下しないように、定期的に掃除を行う」といったポイントを押さえておきましょう。
また、衝撃や振動を与えないように、「安定した場所に保管する」「衝撃を吸収してくれるケースで持ち運ぶ」など、保管や移動方法を工夫することも大切です。
データを分散して保存する
SSDには読み書きできるデータ量の上限があるため、1台当たりの読み書き量を減らすことも大切です。
外付け、またはクラウドストレージにデータを分散させ、SSDへの書き込み量を減らしましょう。
たとえば、OSや重要なソフトウェアはSSDを活用し、ドキュメント類や写真・動画などは他のストレージに保存するといった方法が考えられます。
SSD以外のバックアップ方法は?

重要なデータは破損や消失に備えて定期的にバックアップを行うことが大切です。SSDは優れたストレージデバイスですが、今回紹介したように寿命によってエラーが発生することも考えられます。
バックアップがないと一度失われたデータは元に戻りません。以下のような方法でバックアップを行いましょう。
【HDD(ハード・ディスク・ドライブ)】
外付けHDDはパソコンやテレビなど、データの保存方法として広く普及しているストレージデバイスです。衝撃や振動に弱いというデメリットはあるものの、大容量モデルでも比較的お手頃な価格で入手できるので、持ち運びをしない場合は外付けHDDにデータをコピーしバックアップするのをぜひ検討してみてください。
【USBメモリ】
USBメモリは、小型で持ち運びがしやすいストレージデバイスとして人気のアイテムです。パソコン全体のバックアップには適していませんが、短期・少量のデータの持ち運び用には重宝します。
【クラウドストレージ】
クラウドストレージは、インターネット上にデータを保存するサービスです。Google ドライブやOneDrive、Dropbox、iCloudなどが代表的で、スマートフォンやパソコンなど、複数のデバイスから手軽にアクセスできます。
「容量を増やすには課金が必要」「オフラインでは利用できない」といったデメリットがありますが、外部端末の準備が不要なほか、外的環境に左右されないというメリットもあります。
なお、バックアップ方法や用途別の使い分けを詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてチェックしてみてください。
関連記事:パソコン・スマホにおすすめのバックアップ方法とは?
関連記事:USBメモリとスティック型SSDの違いは? SSDでパソコンの動きを高速
化しよう
関連記事:SSDとHDDの違いとは?それぞれのおすすめの利用方法
まとめ
一般的にSSDの寿命の目安は5~10年とされており、この目安はTBWとDWPDという指標から計算されています。SSDのTBWとDWPDは、取扱説明書やHP等で確認できるため、お使いのSSDの寿命を知りたい方はチェックしてみましょう。
ただし、SSDの寿命は使い方や保管方法によって左右されます。SSDを長持ちさせたいという方は、今回紹介したポイントを実践してみてください。
【関西でネット回線をお探しなら】
eo光は18年連続お客さま満足度 No.1!※
※RBB TODAY ブロードバンドアワード2024 キャリア部門 エリア別総合(近畿)第1位(2025年1月発表)
2007年~2024年18年連続受賞。
※上記掲載の情報は、取材当時のものです。掲載日以降に内容が変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。